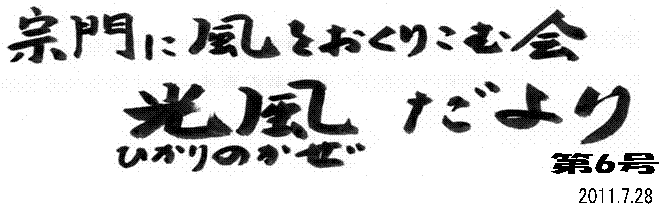
浄土を願う人々
珠洲市で起こった反原発運動の中で、可能性調査の作業車の前に飛び出し、車の前で大の字になった一人の老婆の姿があった。「ひくならひいてみろ。おら(わたし)のいのちひとつで原発がとまるんやったら、これで子どもたちや孫たちに顔向けができるんや。さあ、ひけ!」という、いのちを紡ごうとする人々の姿があった。また、作業員に合掌しながら、「ありがとう、本当にありがとう。あんたらが原発の問題を持ってきたおかげで、わしはここに大事な宝があることを忘れとったことに気がついた。自分を育ててくれたこの海と山や。この宝をそのまま子や孫たちに渡すことがわしの仕事やった。もう十分やから、どうぞお帰りください」という老人たちの姿があった。これらの言葉は、高度経済成長以降、「一歩でもいいから金沢に近いところに嫁に行け」と言い続けてきた人々の中から発せられた言葉である。その人々の姿は、原発を過疎地という弱者に押しつける者たちに対する怒りであると同時に、それを受け入れてきた自らの価値観・生き方、そして歴史を問い直す作業を意味していた。そしてそれは、人間が人間であるために何をいちばん大事なこととしていくかを確認していく作業でもあったのである。
さまざまな運動に関わる中で、自分の価値観や生きる方向が課題になり、根源的な問いを持って生きる人々がいる。親鸞が出会った人々とは、そんな人々ではなかったのか。そして、その姿こそ浄土を願う人々と親鸞が見いだした人間の姿ではなかったのだろうか。 (真宗ブックレット9『いのちを奪う原発』より抜粋)
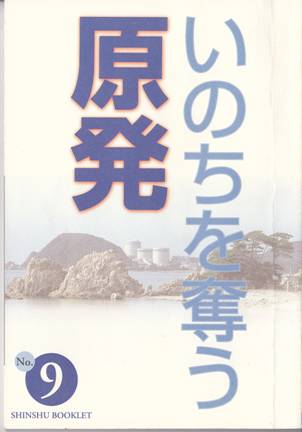
はじめに
議会(常会)が6月22日から29日まで開かれました。前年、不本意ながら2010年・2011年の2ヵ年の予算が議決されたため、議事日程は2009年度決算、2010年度・2011年度の補正予算、条例案の審議内容でした。すべて、当局提案通り可決されました。
(興法議員団41人 無所属クラブ12人 恒沙の会9人 無所属3人)
2009年度決算(賛成)
歳入 9,654,593,043円
第54回宗 歳出 9,071,693,064円
差引 582,899,979円
291,449,990円 平衡資金へ
291,449,989円 2011年度へ
2010年度宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計補正予算(賛成)
歳入 4,832,269,644円
歳出 4,832,269,644円
2011年度補正予算(賛成)
歳入 8,481,449,989円
歳出 8,481,449,989円
地震災害による当該教区減免措置分100,000,000円
(内訳・平衡資金6,000万円+宗務諸費抑制2,000万円+宗務職員給与抑制2,000万円)
? 現地復興支援センターボランティア活動費
被災教区教化助成費
救援物資備蓄費等
2011年度宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計補正予算(賛成)
歳入 2,578,810,434円
歳出 2,578,810,434円
御正当報恩講を御遠忌の一環としての位置づけにする。
御正当報恩講費 58,500,000円
御遠忌讃仰音楽法要費 17,000,000円
地震災害物故者追弔法会(被災者支援コンサートを含む)
25,500,000円
法要全体 121,300,000円増額
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計収入支出総計画変更案(賛成)
収入 33,950,000,000円
支出 33,950,000,000円
当初予算から、完納寺院超過額280,000,000円の増収のため。
|
|
|
「頭の上に広がる重さは相変わらずですが、ともかく日常をこなしております。でも、その日常は普通ではないのです。極度の緊張状態の上に、ふわっと乗せただけの普通です。被災した誰もが先の見えない不安の中にいると思いますが、原発災害はまた違った被災のありようだと思います。どんなにがんばっても、復興復旧を自分たちの力で成し遂げることができないのですから。いまだぎりぎりのところで留まらざるを得ない人たちについて、一刻も早く助けの手を差し伸べてほしいと切に願います。警戒区域の一時帰宅や計画的避難区域でこれから出ていく人たちの姿を見るにつけ、その土地で人が生きるということは理屈ではないのです、肌で感じるのです。心の奥底で血の涙を流しながら留まっている人、また、苦渋の中、家を離れるのです。考えれば考えるほど、不安で苦しいことだらけです」。
福島県に住む友からの便りです。大地震・津波・原発崩壊は緑の大地を茶色に変えてしまいました。そして、友の心は灰色にしずみました。でも、友は茶色の大地と灰色の心から夫とともに新しい歩みをすると最後に添えてありました。私はこの便りにいまだ返す言葉を持ちえていません。
10年前「宗祖親鸞聖人の750回御遠忌基本計画策定委員会」が組織され、御遠忌をどのようにお迎えするのかについて協議し、同朋会運動40年の歩みを問い返しながら「宗祖としての親鸞聖人に遇う」という基本理念が掲げられました。
教団の実現(5)同朋の生活を明らかにする―が挙げられています。これらの基本姿勢はどのように具体的に表現されたのでしょうか。御影堂修復は成り、団体参拝席はほぼ埋まりました。しかし、一般席は空席が目立ち、阿弥陀堂には素屋根のかかったまま、同朋会運動50年を迎えるというのに「宗門白書」も出されず、750回御遠忌法要は勤められました。
顧みれば700回御遠忌を厳修するにあたっての問題提起は、「御遠忌を迎えて、われらは一体何をなすべきかの一途が明らかでない。宗門全体が足なみをそろえて進むべき体制がととのうているとはおもわれない。このままでは御遠忌が却って聖人の御恩徳を汚しはせぬかとの声をも聞き胸をも打たれる次第である」と、宮谷法含総長は、この社会・宗門の状況のままでは御遠忌を勤めることはできない、宗祖に顔向けができないという危機意識を持っての悲痛な表白でした。そして、御遠忌円成後、法主は「御教書」を発せられ、宗門が果たすべき使命は、現実の社会に原理と方向を明らかにするため、まず厳しく内に省み、改めるべきは躊躇なく改めることを示されました。
さて、750回の御遠忌法要ではどのようなことが内外に問題提起され、方向が指し示されたのでしょうか。そして、電通の企画力をどのように評価されているのでしょうか。
られることを忘れてはならないと思います。宗門が2002年に発行した、いえ、1989年に真宗ブックレット第1号として発行されるはずであった『いのちを奪う原発』では、「人間が人間でなくされ、悲しみを奪われていく現実に、驚き、悲しみ、怒り、眼を開かされ、どこまでも批判していくこと。そして一人の人間として生きていく勇気と意欲を取り戻すこと。これこそが親鸞聖人の課題ではなかったのか」と、すでに提起されています。大震災から100余日が経ち、遅きに失してはいますが、今こそ、宗門は国内外に向かって、刻一刻に深刻化する福島原発のありさま、出続ける放射能、校庭に響く子供たちの声も聞けない、悲しみと苦悩の渦巻く同朋を前に、声明を発する時剋です。宗派として「学ぶ」という姿勢、「聞く」ということを堅持していく、それを拒むものではありません。が、その声明を出すか否かは、この教団が宗教的生命を放棄する姿になるか否か、国策に追従するか否かにかかわるといっても過言ではないと思います。
まさにいのちを課題にする原発の問題について、今、宗門から声明を出される意志があるのかどうかをお尋ねいたします。そして、もし、出される意志がないとするなら、「学びを徹底してから」という悠長な理由以外の理由をお示しください。さらには、願わくば、教学研究所、親鸞仏教センターという教学を荷う部署からの原発問題に対する発信が望まれます。
クアップをする体制の構築が急がれるのではないでしょうか。その方途をお尋ねいたします。
次に御遠忌記念行事のギャラリー展「中村久子展」についてお尋ねいたします。
40年間自らも身体に不自由をもち、障害者の解放運動をされている方から「中村久子展」によせて、東本願寺宛に公開質問状が届いていると聞いております。その返答はいまだ届いてないとのことです。質問の内容は、東本願寺がどういう意図で展示を行ったかという疑問、中村久子さんを美化し、優越感を抱かせるだけであるということ、ヘレン・ケラーが手足のないことを不幸と決め付けたこと、なぜ不幸といえるのか。50年前の社会状況の中で生きられた中村久子さんは立派に生きられたと感じましたが、その表現にはあらゆる障害者が生きていける展示会になっているとは思えない。ただの見世物小屋の発想の展示としてしか感じられない、許しがたい、というものです。展示の意図、あらゆる障害者が生きることのできる展示なのかどうか、このギャラリー展に来場した人たちから感想を求めたかどうかの3点についての質問です。これは、私たち親鸞聖人の教えを少しでも聞いてきたものに対する質問であると思います。絶望することを否定し、これでもかとがんばることをしいてしまうこと、このことが差別を生み出す心であることを知らされるのです。
この公開質問状に対する宗門としての考え、そして、質問にもあるとおり、中村久子展を開催するに当たり、どのようなことを伝えようとされたのか、お尋ねいたします。
電通の手の入らない、解放運動推進本部と女性室スタッフを中心に企画・実行された手作りの「カフェあいあう」が1日平均120人、多い時で300人の来場をえました。総長は法要結願に際してこの「カフェあいあう」が有縁の方々にとって大切な開かれた場になったことは、予期せず、衝撃的なものだったと評価されました。そして、継続したい旨も語られました。言うは易しです。その継続されるための具体的な構想はどのように考えられているのでしょうか。どの部署が担当し、人員はどのように確保していくのか。人と人が出会う大切な場所だからこそ、行き当たりばったりの人的な配置は許されないと思います。丁寧に、関わったスタッフから考えを聞き、進めていかれることを望むばかりです。
|
◆ちなみに、興法議員団は調 紀幹事長 恒沙の会は森島 憲秀さんが代表質問をされました。私は調さんに続いて2番目に登壇しました。議員になって6年目ですが、毎年、ドキドキしながら、自分で作った文なのに噛んでしまう。 まあ、慣れたいとは思いませんが。 |
||||
|
旦保議員の質問に対する総長答弁 「いのちを課題にする原発問題の声明について」 ただいまの旦保議員のご質問にお答えさせていただきます。 私から、原発問題についての声明を出すつもりはないかとのご質問でございましたが、既に御遠忌「被災者支援のつどい」、第2期法要・第3期法要において、原発に依存する私たちのあり方を見直すべきとの表明をさせていただきました。また、このたびの演説におきましても原発の誤謬性について申し述べさせていただくと同時に、誰かを悪者にしなければおさまらないような状況、言わば「人知をもって人知を批判するような立場を離れねばならない」ということを問題提起させていただいたつもりであります。ですから、私から重ねて現段階では声明を出すつもりはございません。 被曝された方々への支援のために、故郷を追われた人々のために、原発に依存する生活を見直すために、今私たちができること、必要なことを学び、一早く実践に移すことが重要であると考えております。以上答弁とさせていただきます。 Ø 思い 3月11日に襲ってきた大地震、大津波と言う悲しい自然災害、それに連動しての福島第一原発事故という人災は「2回目の敗戦」と表現された方がおられます。まさに、国策として、推し進めてきた原子力発電所は大自然の驚異の前に壊滅的な状況となりました。そして、放射能汚染は深刻化の一途を辿っていることは、誰もが知るところです。 そんな中で今こそ声を上げる時機なのではないかと代表質問で問いました。その総長からの答弁が上記です。 私たちは、総長の言われるとおり、「人知」の真っ只中で生活しています。その「人知」がこの原発事故を起こしてしまったのです。私をして原発事故を起こさしめたのです。それを思う時、「人知」のなせるこのありさまを「批判してはならない」というのであれば、「人知」でしか生きられない私を許していくか、現実に目を向けず、蚊帳の外に身を置くことになるのです。そういう自分自身を許す ことはできません。 親鸞さんは、なぜ比叡の山を下りられたか。親鸞さんは、なぜ流罪にあったのか。それを思わずにはおれません。 今、寺の存在は危機の中にあると自らも言 い、さまざまな分野からも指摘されています。しかし、それでもなお、門を閉ざし、口を閉ざしていくのでしょうか。またぞろ、風景としてしまうのでしょうか。 釈尊が「殺してはならぬ 殺さしめてはならぬ」と言われました。それを伝えるのが、聞いた者のお仕事なのではないでしょうか。もし、それを「批判」という言葉で表現されるのであれば、私はその言葉に甘んじたいと思います。 「原子力発電が国策として推進されている今日、私たちにとっての大きな課題です。国策だからよいことだと従うのか、また、仕方がないとあきらめるのか。それとも逆に、国策だからこそ批判的に真向かおうとするのか。問われているのは、私たちの浄土観でもある」と、10年前、東海村JCO臨界被曝事故の時に伝えてくださった先輩の言葉です。
「脱原発社会」実現への決議(案) 2011年3月11日。私たちは、東京電力福島第一原子力発電所事故がもたらした放射能汚染が、未だかつてない愚かな人間の所業として人類史に刻まれたこの日を忘れることができません。 現在、広範な地域の子供たちを含む100万人にも及ぶ住民が、強い放射線にさらされています。大気、土壌、地下水、海水、食物等への汚染は、その人たちに長期にわたる被曝におののく生活を強いることになるのは必至であります。そのうち10万人近い人たちが仕事や生活を奪われ、故郷を棄てさせられ避難を余儀なくされています。 ここに至って、「核の平和利用」「クリーンエネルギー」「電力の安定供給」というスローガンのもと、国策として推進してきた原子力政策の問題の本質とは、「被曝の問題」であることが露わになりました。まさに、原発が生きとし生けるものの「いのち」を奪うことが明白になった今、人間は原発とは共存できないことを、私たちははっきりと見定めなければなりません。 福島原発をはじめとした54基の日本の原発では、ヒロシマ・ナガサキの生存されている被爆者数をはるかに超える労働者が被曝しています。それのみならず、放出された放射能による住民被曝の拡がり、さらには核廃棄物による遠い未来に生まれてくるいのちをも被曝の恐怖にさらすことになります。 原発を支えてきた「安全神話」と「必要神話」という二つの虚構によって覆い隠されてきたものが、いのちへの冒涜であり共に生きあう世界を根こそぎ奪う以外の何ものでもないことが明確になりました。もはや原発を必要とするどのような理由付けも成り立ちはしません。 私たちは「脱原発社会」の実現を目指し、地獄・餓鬼・畜生のない国を希求した浄土の願いに応えるため、宗門を挙げて歩みだすことを全世界に表明し誓うものであります。 2011年6月29日 真宗大谷派 宗議会議員一同
Ø 思い 結果、恒沙・無所属クラブ・無所属の各議員の署名の下(21人)、上記の決議文案を上程し、採決されました。賛成少数で否決となりました。
議事の最後がこの決議であっただけに、閉会後、会派の部屋で怒りと悲しみと落胆で声を張り上げてしまいました。何がどうなのか、まったく理由もわからず、今議会の最重要課題といってもいい案件が、あっという間に否決で終わってしまいました。
議会終了後、何日か経って宗教紙に「決議文否決」の見出しが大きく出、なんともいたたまれない思いをしていました。そんな折り 真宗大谷派 南溟寺住職 戸次公正さんから、真宗大谷派宗議会議員各位と有権者及び宗門人各位に対して、『「<脱原発>決議案の否決」という宗政状況に異義あり』というファックスが届きました(7月8日付け)。2枚のA4紙びっしりの言葉は、私の頭をぶち割りました。
○原案が二つの会派から出されたのを相互に相殺的に否決するのはまことに由々しき怪しむべき事態であります。
○結果的に真宗大谷派の議会が「<脱原発>の決議案を否決した」という宗政の状況だけが表面化してしまったことです。あなた方は、このような事態を招来したことを、自分たちが何をしでかしたのかを本当に分かっておられるのですか?
○各地の原発を抱える地域社会に住む人々への想像力を働かせてこのような「否決」議会を生み出せたのですか?
○私が言いたいのは、否決ではなく可決させるような宗政活動を貫いてほしかったということです。
|
その他の質問に対する答弁
■これから、阿弥陀堂初め修復される建物について、ソーラーを採用していく考えはありますか。
杉浦参務
伝統的建物に(阿弥陀堂・山門等)ついては、考えていないが、教化機能の建物については環境や防災を考えたものにしていく。
■ボランティア支援と仙台の現地復興支援センターの人員の補充や精神的・経済的支援は、長期化の中でどのように考えていますか。
黒川参務
人的には追加派遣を考えている。ボランティアについても炊き出しの食材費などの支援を考えている。
■御遠忌記念行事のギャラリー展「中村久子展」について。この展示を見られた、障害をもたれている方から、公開質問状(4頁参照)が届いていますが、それに対しての返事はされたのかどうか。そして、この展示をするに当たってはどのようなコンセプトであったのか。
林参務
協議を重ねて返答するので、もう少し待ってください、との手紙を出した。コンセプトは彼女を支えた人々や『歎異抄』との出会いをとおして、苦難の境遇と障がいの身の事実を真正面から引き受けて、力強く人生を生き抜かれました、その人に出会ってもらいたい。
■御遠忌期間中、総会所を会場に開かれていた「カフェあいあう」を総長の継続する意思表明に対して、どういう構想をもっているのか。
林参務
出会い・考え・語り合うをテーマに「カフェあいあう」を展開してきました。窓口をはっきりとして、これからのことを検討して行きたい。
可決した条例案
□列座の出向に係る特別措置条例案
現行の別院条例では職員の人事交流が想定されていないが、まず、広域な北海道教区内の別院について地域の特性を活かした共同教化を実現するために、列座の人事交流を可能にしようとするもの。―これによって、別院間の列座の出向を可能にし、地方の弘教の中心としての別院の活性化を強力に促進する第一歩にしたいそうです。「別院問題研究会」で出てきた課題のようです。北海道在住の方がこの条例で何をしたいのかが具体的にわからない、とつぶやいておられました。
□開教条例の一部を改正する条例案
□沖縄開教推進条例の一部を改正する条例案
海外開教区の別院住職を補佐する役職として「開教司教」を新設するというもの。そして、開教司教は開教区の僧侶・門徒の代表として同朋とともに真宗の教法を聞信する。その開教司教は鍵役から宗務総長が任命する、となっています。―鍵役、いわゆる連枝がこれにあたります。今回は門主の従兄弟に当たる方がこの任に就かれるそうです。ブラジルに在住されていて、ポルトガル語・ドイツ語などが堪能だそうです。宗派と開教寺院の関係を明確にするために、この司教なるものを置くそうです。「鍵役」の任は海外を巡回しながら勤まるのでしょうか。また、「開教司教」設置について、海外開教寺院に住まいしながら、地域の方々との交流をはかっておられる人たちの意見の聴取はされたのかどうか。なぜ、条例を改正しなければならないほど、この役職を設置しなければならないのかが不透明でした。
◆議会が開かれるたびに、当局から、条例案がいくつか上程されます。その条例案は、実働していく上での整合性のために改正(改正と思われない事もありますが)されていくわけです。しかし、すべての条例案ということではありません
議会傍聴記
茨城一組 円鏡寺 佐野和子
今回で三度目の初日傍聴でした。宗務所に入ったら、ちょっと静かな雰囲気で一瞬、日にちを間違えたかなという思いが横切りましたが、すぐ知人に声をかけてもらい、一安心。所内は節電中とあって、議場も少々暑かったのには忍の一字。議員の方々始め関係者の皆様方も、間衣輪袈裟で大変だったのでは。
事務局からの報告などの後、総長演説、休憩を挟んで財務長演説と粛々と読み上げられていきました。今回は十年の準備期間をかけた宗祖の本山御遠忌法要後の総括的宗会ということだったのでしょうが、直前に東日本大震災に遭遇したことによって、被災地被害の甚大さを受けての重い宗会になったような気がしました。静かと感じた雰囲気はこういう事態の影響もあったからでしょうか。地元茨城県も被災地と認定されました。
地震・津波は地球の自然現象であり、私たち人間が左右できるものではありません。一方、原子力発電は私たち人間がつくったものです。自然災害が引き金となって起きた原発の事故とはいえ、人間の五感では捉えられない放射能汚染から身を守ることは難しいし、収束までにかなり時間がかかるという情報を聞きます。
こういう状況だけを特別視するわけではありませんが、「宗門の存立の本義を現代に顕現し、宗門が負荷する大いなる使命を果たす」という宗憲前文の願いをよくよく思慮しなければならないということを感じました。
東京五組 道教寺(副)住職 須賀 力
今年の常会は、御遠忌の開催にあたって、約半月遅れの6月22日宗務総長の演説に始まった。
遡ること、6月14日、東京教区では、昨年から始まった「宗会に臨む会」が開かれた。
御遠忌と震災、東京教区では被災された寺院があり、そして仙台教区とは隣教区ということもあり、今後の本山の被災地への動向も気になっており、その中、宗務総長が京都新聞での対話の中で「人知の闇」という言葉が取り上げられていた。
今年は、旦保立子議員の代表質問が行われた6月24日に傍聴をした。御遠忌後?ということで一昨年からの通達で、会期を遅らせ、さらに1週間(通常は約2週間)と短縮した開催、さらには福島第一原発の事故の影響で、各会派の部屋の温度設定は28度。エアコンよりも窓を開けた外気の方が涼を感じつつ、議場に至っては傍聴席が後方の一段高いところにあり、MOROに議員各位の熱気が伝わり、30度を越え、扇子で扇ぐことも禁止のなか行われた。
旦保議員は、福島県に住む友人の手紙の紹介を皮切りに、御遠忌について質問し、宮谷内局時代の「宗門白書」をあげ、安原総長に
東日本大震災の今後の宗門の動向、原子力問題についての声明、屋根瓦ソーラー化問題について、ボランティア支援を始めとする災害復興支援について、御遠忌記念事業の「中村久子展」「カフェあいあう」について、質問した。
答弁した総長、参務からは、原発についての研修を今後、全国規模で行っていくこと、原子力についての総長声明は今後出さない意向を述べ、参務からは阪神大震災を踏まえ今後、出来る限りの支援を行う意向を述べた。「中村久子展」については今後調査をすることと、「カフェあいあう」については今後も開催(具体的にいつどこでについては無かった)する旨が述べられた。
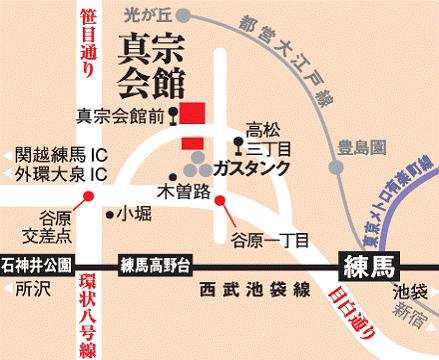 東日本大震災の復興への兆しは、まだまだ遠く感じるなか、どう宗門は対応をしていくのか、そろそろ各教区の資金源が乏しくなる中、我々は一抹の不安を抱えざるを得ない。早急の宗門の対応、取り組みを願うばかりです。
東日本大震災の復興への兆しは、まだまだ遠く感じるなか、どう宗門は対応をしていくのか、そろそろ各教区の資金源が乏しくなる中、我々は一抹の不安を抱えざるを得ない。早急の宗門の対応、取り組みを願うばかりです。
おわりに
毎年5月最終週から6月二週目までの常会(宗議会)期間が、今年は御遠忌法要のため、6月22日から29日までの8日間となりました。3月11日以来、私たちの生活、心は大震災・大津波・福島第一原発抜きには語れなくなっていました。当然、議会もそのようになりました。
御遠忌はどうであったのか、被災者に対する対応は、原発に対する考えはどうなのか、そういう質問が大半を占めました。
阿弥陀堂には素屋根がかかったまま、そして、課題となった御影堂外陣の上の「見真額」は掲げられたままで御遠忌法要は終わりました(11月28日御正当報恩講も含めれば終わったとは言えないかもしれませんが)。もちろん、御遠忌法要といっても、被災者に思いを馳せながらの法要は荘厳・儀式全般にわたって、相当に変更しての執行となりました。そして、「御遠忌は中止し、延期すべきだった」「ご遠忌は御遠忌として予定通りの日程と次第でやるべきだった」「第一期を被災者のつどいにして
いただいたのはうれしかった」など、それぞれに思いがありました。
私は両堂の修復が決定された頃から、すべての修復が終了してから、御遠忌は勤められるのがいいと思っていました。そんな時、ある門徒さんが「御遠忌を延ばしても親鸞さんは怒られないですよ」と言われたのを忘れることができません。
700回の御遠忌法要終了後の宗議会冒頭で訓覇信雄総長は“現実の社会に原理と方向を与えることにより、世界に応える教団の形成を急がねばならない”“世界の現状に応えることのできない教団の遊離した現実の姿が浮かんでくる”と語られました。そして、その視
点から「同朋会運動」(1962年)が提唱されました。
その同朋会運動は50年を迎えます。しかし、50年を経た今、私たちは訓覇信雄氏が憂えた「世界の現状に応えることのできない教団の遊離した現実」は、どういう宗門の姿となって表現されているのでしょうか。私自身、顧みなくてはならないと思います。
平野修氏は蓮如さんの500回御遠忌を「漸愧の御遠忌」と受けとめられました。そして、その時の能邨総長は親鸞聖人、蓮如上人の心に背いた深い漸愧の念から始まらねばならないと、総括の言葉を遺しておられます。
私たちに先んじて、真宗に出会われた方々が「遺教」として語ってくださった提起を私は忘れてしまっていました。
2012年2月、御遠忌総括の臨時宗議会が招集されるそうです。同時に同朋会運動50年、再出発の時です。心して歩みたいと思います。
釈迦如来かくれましまして
二千余年になりたまう
正像の二時はおわりにき
如来の遺弟悲泣せよ
(正像末浄土和讃)
 |